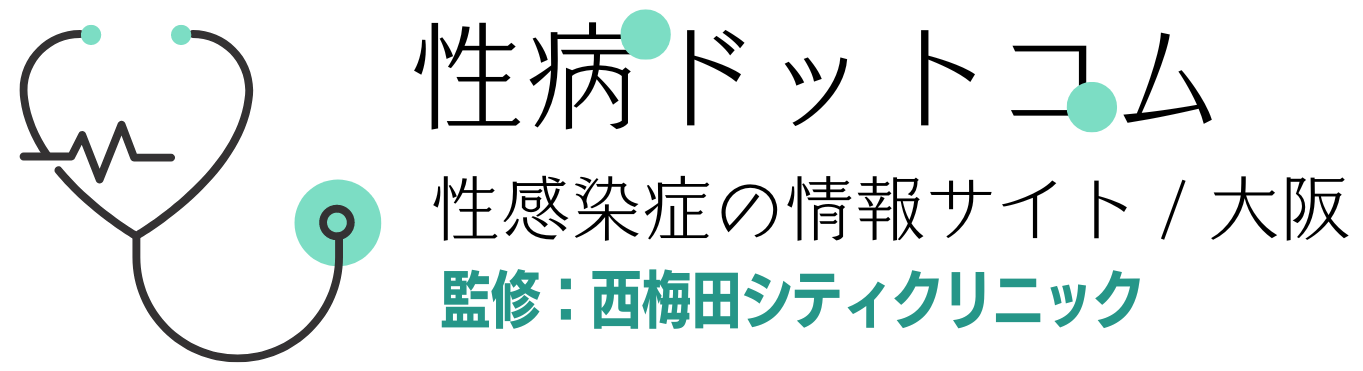もしかして梅毒?気づかないまま進行する危険な症状と検査の必要性

梅毒は性感染症のひとつで、知らないうちに体内に潜伏し、進行すると重大な健康被害を引き起こします。
近年、日本では再び感染者が増加傾向にあり、誰にとっても身近な感染症になりつつあります。
本記事では、梅毒にかかるとどのような症状が出るのか、どんな検査や治療が必要なのか、そして日常生活でできる予防法についてわかりやすく解説します。
自身の健康を守り、大切なパートナーを守るために、正しい知識を持つことが大切です。
梅毒の症状|4期の特徴

第1期(感染後3週間〜3か月)
- 性器・肛門・口などに「硬いしこり(初期硬結)」ができる
- しこりは痛みやかゆみが少なく、気づかないことも多い
- 潰瘍ができると「硬性下疳(こうせいげかん)」と呼ばれる
男性では陰茎や亀頭に、女性では膣内や外陰部に多く見られますが、発見しにくい部位にできると見逃されやすいです。
第2期(感染後3か月〜3年)
- 発熱・頭痛・倦怠感・のどの痛み
- 手のひらや足の裏に発疹(梅毒性バラ疹)
- 脱毛、粘膜のただれ、扁平コンジローマ
一度消えることもありますが、治ったわけではなく、体内では進行を続けています。
第3期(感染後3年以上)
- 皮膚や筋肉、骨、内臓に「ゴム腫」と呼ばれる硬いしこりができる
- 鼻骨にできると「鞍鼻(あんび)」となり、変形や破壊を引き起こす
第4期(感染後10年以上)
- 大動脈瘤、大動脈破裂などの心血管障害
- 神経障害(記憶障害、運動麻痺など)
- 最悪の場合は命に関わる
無症状で進行する「無症候性梅毒」もあり、気づかないまま重症化する危険があります。
検査の重要性|早期発見がカギ
梅毒は症状が軽い、あるいは出ないまま進行することも多いため、検査がとても重要です。
主な検査方法
- TP法:一度感染すると生涯陽性になる。感染歴の確認に有効
- RPR法:感染の有無や治療効果を数値で確認できる
感染機会から4週間以上経過すれば検査可能となります。
感染歴がある人は再検査で数値の変化を追います。
不安な行為があった場合、体調に異変がある場合は、早めに医療機関で検査を受けましょう。
梅毒の治療
梅毒は適切な治療を受ければ治る感染症です。
- 第1期:ペニシリン系抗生物質を2〜4週間服用
- 第2期:4〜8週間の服用が必要
- 筋肉注射を使う場合もある
治療後は約1か月後にRPR検査で効果を確認し、その後も数値の推移を見ながら治癒判定を行います。
治療中に中断したり、再感染したりすると完治が遅れるため、医師の指示を必ず守ることが大切です。
梅毒の予防法
梅毒を防ぐためには日常的な予防が欠かせません。
- コンドームを正しく使用する
- 不特定多数との性的接触を避ける
- 定期的に性感染症(STD)検査を受ける
梅毒は誰にでも感染する可能性があり、「自分には関係ない」と思っていても感染してしまう例は少なくありません。
少しでも不安を感じたら、迷わず医療機関に相談しましょう。
まとめ
梅毒は気づかないうちに進行し、命に関わる病気へと至る可能性のある性感染症です。
しかし、正しい知識を持ち、検査や治療を受ければ回復が期待できます。
- 梅毒の症状は4期に分かれ、長期間かけて進行する
- 無症状でも感染している可能性があるため、検査が重要
- 抗生物質で治療可能だが、再検査と経過観察が必要
- 予防にはコンドーム使用と検査習慣が不可欠
自身の健康、そして大切なパートナーを守るために、梅毒について正しく理解し、適切な予防と早期受診を心がけましょう。

少しでも違和感を感じたら、
一度検査を受けてみませんか?
西梅田シティクリニックで受診をしよう。
少しでも違和感を感じたら、
一度検査を受けてみませんか?
西梅田シティクリニックで受診をしよう。