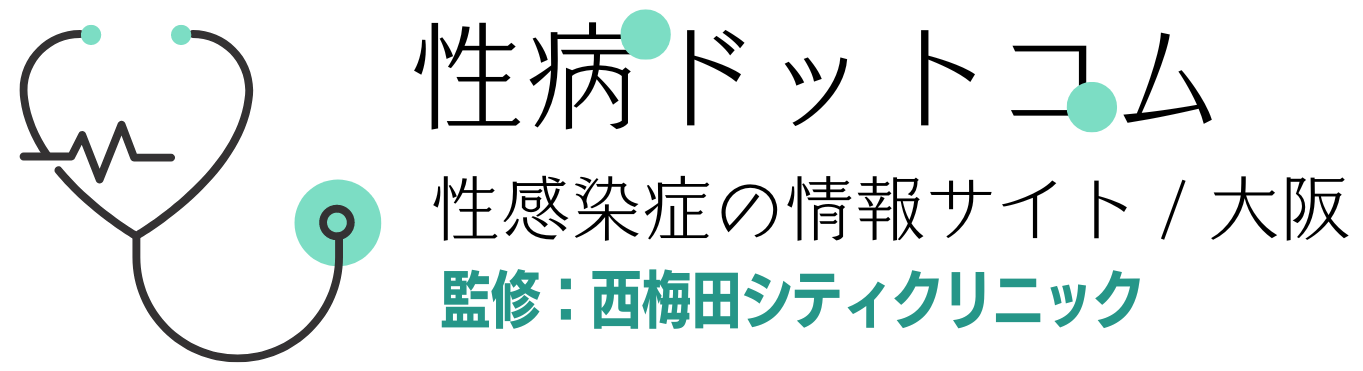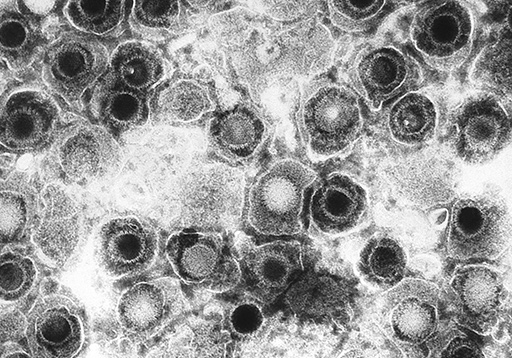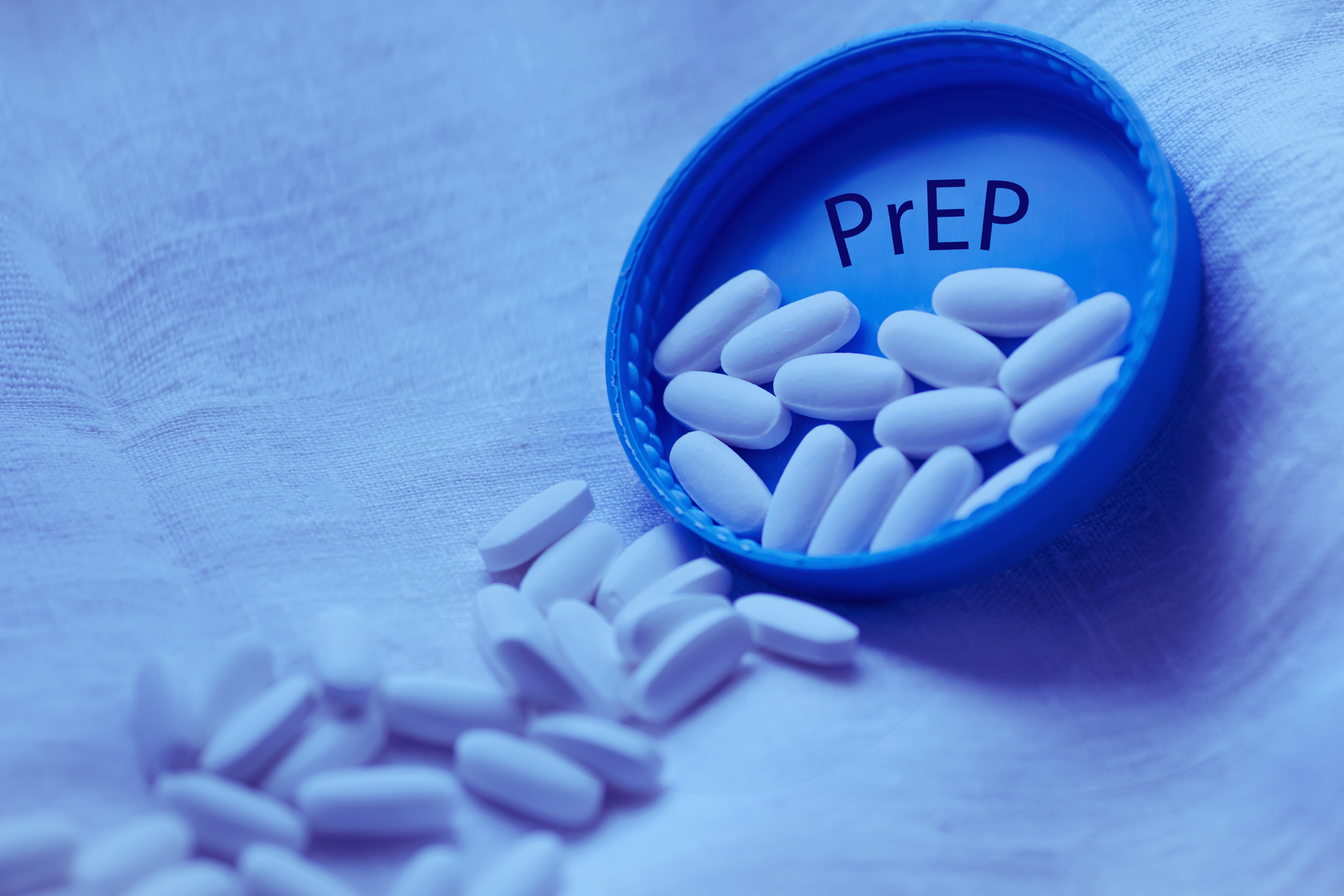口・唇の周りにできものができたら性病を疑うべき?梅毒の可能性も解説

「口や唇の周りにできものがある…これって性病?」
性行為のあとに口や唇にしこりや発疹ができると、不安になる方も多いでしょう。
特に注意したいのは梅毒です。梅毒は自然に治ることはなく、放置すると重症化して命に関わることもあります。初期には口や唇にできもの(硬いしこり)ができることがあり、症状が一時的に消えても治癒したわけではありません。
本記事では、梅毒の特徴や進行段階、検査・治療法、そして予防策について詳しく解説します。
梅毒とは?
梅毒は、梅毒トレポネーマという細菌によって引き起こされる性感染症です。
主に性行為によって感染者の粘膜や皮膚に直接接触することでうつります。
血液や精液、腟分泌液を介しても感染することがあります。
梅毒の感染者数は近年増加傾向にあり、特に2021年以降は急増して社会的にも問題となっています。
梅毒の症状と進行段階

梅毒の症状は4期に分けられます。
第1期(感染から3週間〜3か月)
- 唇・口内・陰部・肛門付近に痛みのないしこり(硬性下疳)ができる
- しこりが潰瘍化・びらん化することもある
- 股の付け根のリンパ節が腫れる場合もある
数週間〜数か月で症状が自然に消えることがありますが、細菌は体内に残っており治癒したわけではありません。
第2期(感染から3か月〜3年)
- 細菌が血流に乗って全身に広がる
- 全身に赤い斑点(梅毒性バラ疹)が出る
- 手のひら・足裏に赤い発疹(梅毒性乾癬)
- 性器や肛門周囲に平らなしこり(扁平コンジローマ)
- 口内に発疹(梅毒性粘膜疹)
症状が多彩で風邪や皮膚病と見間違えることもあります。
第3期(感染から3年以上)
- 筋肉や皮膚に腫瘍(ゴム腫)が出現
- 鼻にできると鼻が変形・欠損することもある
第4期(感染から10年以上)
- 神経や臓器に障害(神経梅毒)
- 大動脈瘤、大動脈炎、麻痺性痴呆、脊髄ろうなど重篤な合併症
- 最悪の場合、死に至る
梅毒検査のポイント

梅毒は血液検査で診断します。主な方法は以下の2種類です。
- TP抗体検査:感染から2か月以上経過した人に有効
- RPR法:感染から1か月〜2か月の人に適応
感染の疑いがある場合は、性行為からの期間を考慮して適切な検査を受ける必要があります。
梅毒の治療法
梅毒は自然治癒せず、抗生物質(ペニシリン系)で治療します。
- 第1期:2〜4週間の服薬
- 第2期:4〜8週間の服薬
- 重症の場合:筋肉注射を行うケースもある
早期に治療を開始すれば治癒率は高いため、症状がある場合はすぐに医療機関を受診してください。
梅毒の予防法
梅毒を防ぐには、以下の対策が有効です。
- 性行為・オーラルセックス時にコンドームを使用する
- 不特定多数との性行為を避ける
- 定期的に性病検査を受ける
特に、風俗業など不特定多数との接触機会がある方は定期的な検査が重要です。
まとめ
口や唇の周りにできものができた場合、梅毒の可能性があります。
初期の症状は自然に消えることもありますが、細菌は体内に残り進行していきます。
梅毒は放置すると全身に広がり、最終的には神経や臓器を侵し、命に関わる危険な病気です。
違和感を覚えたら自己判断せず、必ず医療機関で検査・治療を受けましょう。
自分の健康を守るだけでなく、大切なパートナーを守るためにも、正しい知識と予防行動が欠かせません。

少しでも違和感を感じたら、
一度検査を受けてみませんか?
西梅田シティクリニックで受診をしよう。
少しでも違和感を感じたら、
一度検査を受けてみませんか?
西梅田シティクリニックで受診をしよう。